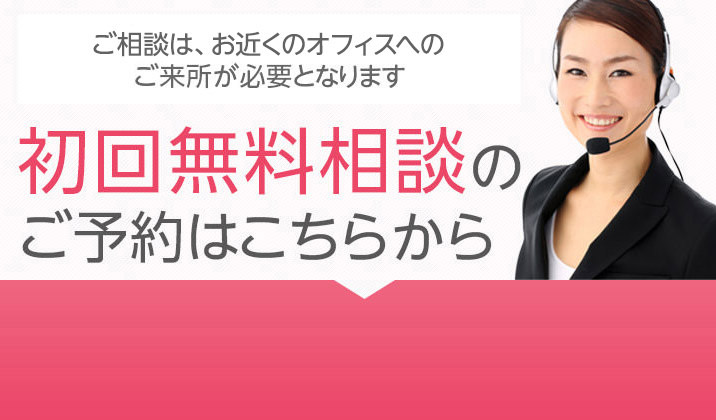離婚した元配偶者の遺族年金はもらえる? 子どもがいる場合の注意点
- その他
- 離婚
- 遺族年金

離婚後に元夫または元妻が亡くなった場合、遺族年金を受け取る権利があるのでしょうか。結論からいえば、元配偶者ご自身は法律上の配偶者ではなくなるため、受給資格はありません。しかし、亡くなられた方との間に子どもがいて、その子どもが実質元配偶者の所得に頼り生活していた場合は、例外的に受給できる可能性があります。
本コラムでは、離婚後に遺族年金を受け取れるケースから優先順位、離婚時に決めておくべきことなどについて、ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスの弁護士が解説します。


1、遺族年金とは? 制度の基本情報
-
(1)遺族年金の種類
遺族年金とは、故人と生計を共にしていた遺族に支給される年金のことです。「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、故人の納付状況により種類が決まります。
- 遺族基礎年金…国民年金に加入していた被保険者の遺族に給付されます。
- 遺族厚生年金…厚生年金に加入していた被保険者の遺族に給付されます。
一般的に、会社員は国民年金と厚生年金の2種類を納めているため、その遺族は遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類が給付されます。一方、厚生年金に加入していない自営業者の場合などは、遺族基礎年金のみが適用となります。
-
(2)遺族年金は残された家族のための制度
遺族年金の趣旨は、残された家族が経済的に困窮しないようにすることです。そのため、遺族年金の支給対象は、故人と生計維持関係があった人となります。
ここでいう、生計維持関係とは
- ① 生計が同一であること
- ② 受け取る人の前年の収入や所得が一定額以下であること
のふたつの条件を満たした関係です。
「生計が同一である」とは、住民票で同じ世帯にいたり、住民票上同じ住所に住んでいることなどを指します。
「収入や所得が一定額以下である」とは、前年の収入が850万円未満であったり、前年の所得が655.5万円未満であったりすることです。なお、令和7年の年金制度改正によりこの年収制限については撤廃される見込みですが、施行日は令和7年3月時点で未定となっています。
遺族年金を受け取るためには、前述のとおり個人との生計維持関係があったことが必要です。
2、遺族年金を受け取るための必須条件
それでは、どのような場合に遺族年金を受け取ることができるのでしょうか。受給するには、亡くなった被保険者側と遺族側の双方がそれぞれ要件を満たしている必要があります。遺族年金の種類ごとに解説しましょう。
-
(1)遺族基礎年金の場合
まず、遺族基礎年金が支給されるには、故人が以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。
国民年金の加入期間が25年以上あること(ただし、保険料免除期間を含んだ納付済期間が加入期間の3分の2以上とする)
老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある場合
次に、受給する遺族側の要件としては、国民年金の被保険者であった故人によって生計を維持されていた
- ① 子のある配偶者
- ② 子
となります。
この場合の「子」とは、未婚かつ、以下のいずれかに該当する場合をいいます。
- 18歳になる年度末の3月31日を経過していない
- 20歳未満で障害等級が1級もしくは2級
そして、この「配偶者」には、故人の生前に離婚していた元配偶者は含まれないため、遺族基礎年金を受給できません。
一方、子は両親の離婚後であっても親子関係はなくならないことから、上記の要件を満たしている「子」は、遺族基礎年金を受給できる可能性があります。もっとも、これら要件を満たす場合であっても、受給できない場合があるため、詳細については、専門家へご相談ください。 -
(2)遺族厚生年金の場合
遺族厚生年金が支給されるには、故人が以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。
- 厚生年金保険の被保険者期間中の病気あるいはケガが要因となり、初診日から5年以内に亡くなった場合(ただし、保険料免除期間を含んだ納付済期間が加入期間の3分の2以上とする)
- 1級または2級の障害厚生年金を受け取っていた場合
- 老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある場合
受給できる遺族側の要件としては、
厚生年金の被保険者であった故人によって生計を維持されていた- 妻(ただし30歳未満で子がいない場合は、5年間の限定給付)
- 孫(ただし前述の遺族基礎年金と同じ条件)
- 55歳以上の夫、父母、祖父母
となります。
具体的な支払い状況にもよりますが、元配偶者から子どもの養育費などが支払われていた場合、生計維持関係があるとみなされる可能性があります。。
また、遺族厚生年金は、子どもがいない妻の場合でも受け取ることができます。
お問い合わせください。
3、離婚後に受け取れる可能性は? 遺族年金の優先順位
離婚した元配偶者の遺族年金を受け取るには、子どもが条件となることが分かりました。
では、遺族年金の受給資格対象が複数いた場合の優先順位を解説しましょう。
今回は、元配偶者の子どもと再婚相手との関係について解説します。
●遺族基礎年金の場合
遺族基礎年金受給の優先順位は、
- ① 子のある配偶者
- ② 子
です。
前でも述べたように、遺族基礎年金の受給資格は、子どもがいる場合のみです。そのため、再婚相手は、故人との間に子どもがいない場合、そもそも遺族基礎年金を受け取ることができません。したがって、故人と元配偶者との間に子どもがいる場合、遺族基礎年金はその子どもに支給されます(ただし、支給されない場合もあります。)。
しかし、再婚相手と元配偶者の双方との間に子どもがいる場合、子のある配偶者(①)は、子(②)に優先しますから、再婚相手に優先的に支給されます。この場合、再婚相手への支給が停止等にならない限り、元配偶者の子どもは遺族基礎年金を受給できないとされています。
●遺族厚生年金の場合
遺族厚生年金受給の優先順位は、
- ① 子のある配偶者
- ② 子
- ③ 子のない配偶者
です。
遺族厚生年金の支給順位も、遺族基礎年金の優先順位と同様です。具体的には、子のある配偶者(①)は子(②)よりも優先されます。したがって、再婚相手と元配偶者の双方に子どもがいる場合、再婚相手が優先されるため、再婚相手への支給が停止にならない限り、元配偶者の子どもには支給されません。
それでは、再婚相手には子どもがいない場合で元配偶者との間に子どもがいる場合、優先順位はどうなるのでしょうか。この場合、遺族厚生年金は、遺族基礎年金と異なり、子のない配偶者(③)にも受給資格がありますが、子(②)は子のない配偶者(③)に優先します。したがって、この場合、元配偶者の子は、再婚相手に優先して遺族厚生年金を支給されることになります。
なお、子どもがいない場合の優先順位は、配偶者(再婚相手)→父母→孫→祖父母となります。
再婚していなかったとしても、次に優先されるのは父母であり、離婚した元配偶者には受給資格がありません。
詳細については、専門家にご相談ください。
離婚してご自身が子どもを育てている場合、遺族年金が受給できるかどうかは気になるところでしょう。なかには、児童扶養手当を受け取っている方もいると思いますが、遺族年金と児童扶養手当は、遺族年金の月額が、児童扶養手当の月額を上回る場合は、同時に受け取ることができないので注意が必要です。遺族年金を受け取るためには、児童扶養手当の金額が減額、もしくは支給停止となる可能性があります。
4、離婚後の生活を守る! 遺族年金以外に請求できるお金
遺族年金を受け取れるかを確認することも大切ですが、離婚後の生活を安定させるためには財産分与や養育費など、現時点で得られるお金について知っておくべきでしょう。
本章では、離婚時に話し合うべきお金について、項目別に解説します。
-
(1)養育費
子どもがいる夫婦が離婚する場合、子どもを育てる親に対して、もう一方が養育費を支払わなければなりません。
養育費の金額は、夫婦の事情によりさまざまなので、一概にいくらとは言えません。しかし、協議時にある程度の目安となるよう、裁判所では養育費・婚姻費用算定表を公表しています。この算定表は、協議がまとまらず裁判所に調停を申し立てた場合に、裁判所が金額判断の基準とするものです。
当事務所でも、請求可能な養育費の目安が簡易的に確認できる、「養育費計算ツール」を公開しています。
どのくらい養育費を得ることができるのか、概算が知りたい方はぜひご利用ください。 -
(2)財産分与
財産分与とは、結婚生活で夫婦が共同して築いた財産を離婚時に分けることです。原則として、1/2の割合で分けられます。
専業主婦(主夫)の場合、家庭にお金を入れていないから、分与額が少なくなるのでは?と心配される方もいらっしゃいますが、この場合、専業で家事を行うことにより、外で働くパートナーを支えていると考えられます。仕事をしていなかったから半分以下になる、いうことはありません。
また、離婚後に生活が苦しくなることが分かっていたり、離婚原因が相手の不貞であった場合には、財産分与額が増額できる可能性もあります。(前者を扶養的財産分与、後者を慰謝料的財産分与と言います) -
(3)年金分割
年金分割とは、相手が厚生年金に入っている場合、その年金を分割することです。当事者で話し合い分割割合を決める合意分割と、話し合いをせずに扶養されていた人の方から半分に分割するよう求める3号分割の2種類があります。この2種類のどちらを申請するべきかは、対象となる期間や条件などに細かな違いがあるため、ご自身の状況に合わせて判断していきましょう。
ただし、どちらの分割方法を選んだとしても、離婚から2年以内に請求する必要があります。その点、注意が必要です。 -
(4)慰謝料
離婚の原因が相手の不貞行為であったなど、相手に責任がある場合、慰謝料を得られる可能性があります。その金額は、個々のケース(年収や、有責の割合など)によりさまざまです。
交渉の仕方次第で得られるかどうか、またその金額が変わってきますので、詳しくは弁護士に相談されることをおすすめします。 -
(5)婚姻費用
離婚が成立する前に別居を始める場合には、収入の少ない方から収入の多い方へ、成立するまでの生活費を請求することができます。これを婚姻費用と言います。その金額は、基本的には、夫婦間での話し合いで決まります。なお、話し合いでまとまらなかった場合には、裁判所に調停や審判を申し立て、支払いを求めます。この裁判所が婚姻費用を決める基準は、一般に公開されていますので、それを基準として話し合いをすることもできるでしょう。
なお、ベリーベスト法律事務所では、「婚姻費用計算ツール」を公開しています。
気になる方は、ぜひご利用ください。 -
(6)ひとり親に対する行政の助成
離婚してひとりで子どもを育てることになった場合、行政に対して経済的な支援や自立に向けた支援を求めましょう。
たとえば名古屋市では、ひとり親向けに市営住宅をあっせんしていたり、ひとり親家庭手当を設けたりしています。
役所では相談窓口も設けられていますので、どのような支援が受けられるか、確認してみるとよいでしょう。
このように、遺族年金以外にも、離婚時に考えるべきお金の問題はたくさんあります。離婚後の生活を安定的に送れるよう、弁護士に相談し相手と交渉することが大切です。
5、まとめ
離婚後は原則として元配偶者の遺族年金を直接受給することはできません。しかし、離婚後であっても子どもがいる場合には子どもを通じて間接的に受給できる可能性があります。ただし、元配偶者の再婚状況や子どもの有無によって受給の可否が変わるため、個別の状況に応じた判断が必要です。また、児童扶養手当との併給調整にも注意が必要となるといえるでしょう。
また、年金制度は随時改正されており、令和7年中にも改正される可能性があります。最新の法令に基づく遺族年金の受給資格や具体的な手続きについては、ご自身の状況に合わせて年金事務所などへご相談ください。
なお、離婚後の生活を安定させるためには、遺族年金以外にも、養育費や財産分与、年金分割など離婚時に確保できる経済的支援制度を適切に活用することが重要です。離婚後であっても請求できる可能性があります。養育費や財産分与などについて請求したいとお考えであれば、離婚問題についての知見が豊富なベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスの弁護士にご相談ください。あなたの状況に適したアドバイスを行うことはもちろん、ご依頼いただいた場合は交渉から対応します。
※現在、ベリーベスト法律事務所では遺族年金の問い合わせを承っておりません。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています