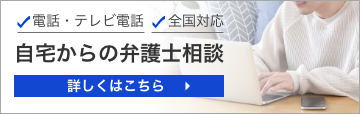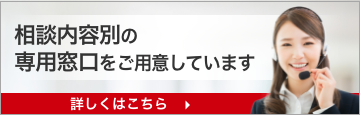二重価格表示とは|景品表示法や違反事例について
- 一般企業法務
- 二重価格表示
- 違反事例

令和5年度に名古屋市消費生活センターに寄せられた消費生活に関する相談は1万2998件でした。
「二重価格表示」とは、実際の販売価格とそれよりも高い価格を併記して、割引商品であることをアピールする表示です。二重価格表示の方法に不適切な部分がある場合は、景品表示法違反を指摘されるおそれがあります。
本記事では、二重価格表示に関する景品表示法の規制内容や違反事例などを、ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスの弁護士が解説します。
1、二重価格表示とは? 景品表示法による規制のポイント
実際の販売価格とそれよりも高い価格を併記して、割引商品であることをアピールする表示は「二重価格表示」と呼ばれています。
不適切な方法で二重価格表示をすると、景品表示法違反を指摘されるおそれがあるので注意が必要です。
-
(1)景品表示法とは
景品表示法とは、事業者による不当な景品類の提供や不当表示を規制する法律です。
商品やサービスに関してあまりにも高額な景品類を提供したり、実態に反する誇大広告をしたりすることは、景品表示法によって禁止されています。
事業者によるこれらの行為は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあるためです。 -
(2)二重価格表示の定義
景品表示法違反が問題になり得る価格表示の例として、「二重価格表示」が挙げられます。
二重価格表示とは、販売価格に当該販売価格よりも高いほかの価格(=比較対照価格)を併記する価格表示のことです。
たとえば、「1万円」という価格を二重線で消した上で「8000円(20%オフ)」と記載する場合などが二重価格表示に当たります。
二重価格表示の主な目的は、実際の販売価格の安さを強調することです。二重価格表示が適正に行われることで、一般の消費者が適正な商品選択をでき、事業者同士の価格競争が促進することが期待できます。
ただしその反面、二重価格表示の方法が不適切な場合には、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与えるおそれがあります。 -
(3)二重価格表示は有利誤認表示に当たることがある
景品表示法では、商品やサービスの価格その他の取引条件について、実際のものまたは競合他社のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認させる表示(=有利誤認表示)が禁止されています(景品表示法第5条第2号)。
二重価格表示についても、比較対照価格の内容について適正な表示が行われていないときは、有利誤認表示として景品表示法違反を指摘される可能性があります。
2、二重価格表示に関するガイドライン|不当表示かどうかの判断基準と違反事例
消費者庁は、事業者が順守すべきガイドラインとして「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」(以下「価格表示ガイドライン」といいます。)を公表しています。
価格表示ガイドラインでは、二重価格表示が景品表示法違反の有利誤認表示に当たるかどうかについて、判断基準を具体的に示しています。
参考:「不当な価格表示についての景品表示法上の考え方」(消費者庁)
-
(1)異なる商品の価格を比較対照価格とする場合
異なる商品の価格差には商品の品質等の違いも反映されているため、価格差のみをもって販売価格の安さを評価することが難しく、不当表示に該当するおそれがあります。
【不当表示に該当する可能性が高い表示の例】- 新品と中古品の価格を並べて表記している場合
- 野菜や鮮魚などの生鮮食料品について二重価格表示をする場合
ただし、同じ事業者が実際に販売している2つの異なる商品について、現在の販売価格を比較することは通常問題ないとされています。
-
(2)過去の販売価格等を比較対照価格とする場合
ある程度の期間にわたって販売されていない価格を、比較対照価格に用いる場合には、不当表示に該当するおそれがあります。
具体的には、比較対照価格での販売実績がない場合は、有利誤認表示に該当する可能性があります。
また、販売実績があるとしてもかなり前の時期の場合には、当該価格がいつの時点でどの程度の期間販売されていた価格であるかなどを正確に表示しない限り、不当表示に該当するおそれがあると指摘されています。
さらに、セール実施の決定後に販売を開始した商品の二重価格表示は、セール前の価格によって実績作りをしていると見られるため、セール前価格の販売期間を正確に表示したとしても、不当表示に該当するおそれがあるとされています。【不当表示に該当する可能性が高い表示の例】- 「紳士スーツ 通常価格5万8000円のところ、4万円」と表示しているが、通常時の販売価格は4万5000円だった場合
- 「羽毛布団 通常価格1万5800円のところ、1万2000円」と表示しているが、実際にはその羽毛布団は初めて販売されるものであった場合
-
(3)将来の販売価格を比較対照価格とする場合
「将来は高くなるので今買うべき」という印象を与える目的で、将来の時点における販売価格を併記した二重価格表示をするケースが見られます。
このような二重価格表示について、比較対照価格によって実際に販売する予定がないときや、ごく短期間のみ比較対照価格で販売するにすぎない場合などには、不当表示に該当するおそれがあると指摘されています。
逆に言えば、もしかりに将来の価格を表示した場合は、その変更時期と価格変更を絶対に守らなければならなくなると意識すべきです。【不当表示に該当する可能性が高い表示の例】- 「婦人ブラウス お試し価格2800円(○月○日以降は6000円)」と表示しているが、実際には○月○日以降も2800円で販売する場合
-
(4)事実に反した希望小売価格を比較対照価格とする場合
製造業者・卸売業者・輸入総代理店などによって設定・公表されたものではない価格を、希望小売価格と称して比較対照価格に用いる場合には、不当表示に該当するおそれがあると指摘されています。
なお、製造業者等が一般消費者向けではなく、小売業者に対して提示している価格を比較対照価格に用いる場合、「希望小売価格」と誤認されないよう、注意して表示する必要があります。【不当表示に該当する可能性が高い表示の例】- 「全自動洗濯機 メーカー希望小売価格7万5000円のところ、5万8000円」と表示しているが、製造業者等が実際に設定した希望小売価格は6万7000円である場合
- 希望小売価格が設定されていない場合に、任意の価格を希望小売価格として比較対照価格に用いる場合
-
(5)事実に反した競合他社の販売価格を比較対照価格とする場合
同一の商品について、競合他社が実際に最近用いている販売価格とはいえないものを比較対照価格に用いるときは、不当表示に該当するおそれがあると指摘されています。
特に、市価を比較対照価格に用いるときは、販売地域内において相当数の競合他社が実際に販売している価格を正確に調査しない限り、不当表示に該当するおそれがある点に注意が必要です。【不当表示に該当する可能性が高い表示の例】- 「陶製人形 市価9000円のところ、3500円」と表示しているが、販売地域内のほかの人形店において、最近では同じ人形が3000円から4000円程度で販売されていた場合
-
(6)実態に反したほかの顧客向けの販売価格を比較対照価格とする場合
それぞれの販売価格が適用される顧客の条件の内容などについて、実際と異なる表示やあいまいな表示を行うときは、不当表示に該当するおそれがあります。
【不当表示に該当する可能性が高い表示の例】- 「K18ダイヤモンドピアス 非会員価格5万円、会員価格2万4980円」と表示しているが、購入を希望する一般消費者は誰でも容易に会員となることができ、非会員価格で販売されることはほとんどない場合
3、不当な二重価格表示をした企業が負うリスク
景品表示法違反に当たる二重価格表示をした事業者は、以下のリスクを負うことになります。
消費者庁長官により、二重価格表示の差止めや再発防止などを命じられることがあります(景品表示法第7条)。
② 課徴金納付命令
消費者庁長官により、二重価格表示をしていた期間中の売上額の3%に相当する課徴金の納付を命じられることがあります(同法第8条)。
③ 適格消費者団体による差止請求
適格消費者団体から、二重価格表示の停止や予防、差止めの措置をとることを請求されるおそれがあります(同法第30条)。
④ 刑事罰
有利誤認表示をした者は「100万円以下の罰金」に処されます(同法第48条第2号)。
また、消費者庁長官の措置命令に違反した場合は「2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」に処され、または懲役と罰金が併科されます(同法第46条)。
4、景品表示法のことなら弁護士に相談を
商品やサービスに関する広告の内容などにつき、景品表示法との関係で問題がないかチェックしたい場合は、弁護士に相談するのが安心です。
弁護士は、法的な観点から広告などを精査してリスクを指摘するとともに、問題点の是正方法についても具体的にアドバイスいたします。
また、広告表現のチェック体制を整備したい場合も、弁護士にご相談ください。会社の事業や組織の実情を踏まえて、適切な体制整備ができるようにサポートいたします。
5、まとめ
不適切な方法で二重価格表示を行うと、消費者庁に景品表示法違反を指摘されるおそれがあります。対策として、弁護士のリーガルチェックを受け、適切な方法で価格表示を行うことを検討しましょう。
ベリーベスト法律事務所は、景品表示法に関する企業のご相談を随時受け付けております。価格表示の方法について問題がないかどうかチェックしてほしい企業や、景品表示法に関するチェック体制を整備したい企業は、ベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスへご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています